日商簿記は、経理や会計の基礎を学びたい方やスキルアップを目指す方にとって非常に人気のある資格試験です。ここでは、初めて日商簿記を受験する方に向けて、簿記の種類と受験方法について詳しく解説します。
日商簿記の級位
日商簿記には難易度に応じて級位が設定されています。社会人で簿記を受験する場合はキャリアアップの観点から、一般的には3級から取得していく場合が多いようです。
簿記初級は、日商簿記の級位の中では最も難易度が低く、簿記の基本的な考え方や記録方法を学ぶための入門資格です。
会計の基礎知識を短期間で身につけたい方に適しており、簿記や会計を初めて学ぶ人や学生で会計や経済の基礎を学びたい人、3級を受験する前のステップとして学びたい人に適した試験となっています。
簿記検定の中で最も受験者数が多く、取得すると小規模の企業や個人商店の会計処理が理解できるようになります。
経理業務やビジネスに関する基礎知識が身につくことや、3級から履歴書に記載できるということから就職、転職活動に活かせる武器の1つとしてオススメの難易度です。迷ったらとりあえず3級取ってから考える!も良いのではないでしょうか。
2級以上になると簿記の試験範囲の中に商業簿記、工業簿記と2つの分野を勉強する必要があります。規模としては中小企業~大企業の経理業務に加え、財務諸表の作成と分析によって経営状況の把握や原価計算を身につけることができます。
3級と比較すると専門性が高まり処理が複雑になるので実務に必要なスキルを本格的に学ぶことができます。
日商簿記検定試験の中で最上位に位置する資格で、高度な会計知識と実務能力を問われます。企業会計や管理会計に関する専門知識を深く学び、大企業や上場企業での経理・財務業務、さらには会計士や税理士を目指す上での基礎となります。
難関な資格であるだけに、1級を取得することで専門職への転職活動や昇進、キャリアアップに大きく役立つことが期待できるほか、専門性が高いので起業や独立も視野に入れることができます。
合格率
簿記の合格率は、試験形態や級位、年度や受験者数によって大きく変動する場合もあるためおおよその数値ですが、2024年の平均的な合格率をまとめました。
初級:約60%~65%
3級:約30%~40%
2級:約20%~40%
1級:約10%~15%
簿記は3級から
簿記の初級は年間で約2千人に対し、3級は年間で約28万人が受験している。この受験者数の圧倒的な差から、簿記の資格を取得しようとするほとんどの人が3級からの取得を目指していることが分かります。
合格率は本当に2級と同じ?
上記の合格率で見ると3級と2級の合格率が数字上同じように見えるので、3級の取得が難しいのでは…と躊躇してしまう人もいるかもしれません。
しかし、2級の年間の受験者数は約12万人ほどで、3級に比べると受験者数が減少していることや難易度が上がっていることから、3級を取得している人、あるいは3級の知識を既に有している人が受験している場合が多いと考えられます。
一方で3級は、前述したようにほとんどの人が3級から取得する、つまり全く知識がない状態から取得する人が多い傾向があります。
また、3級は簿記を取る気がなくても学校や職場で受験しなくてはいけないからとりあえず受験する、という人も一定数いるのではないでしょうか。
何が言いたいのかというと、要するに3級と2級では受験者の熱量が違うということです。
2級であれば3級を持っている人たちがさらに専門性を高めるために受験する人が多いですが3級は知識ゼロの人やモチベーションがそこまで高くない人など、いろいろな人が受ける可能性が高いです。合格率が半分以下というのは難易度以外にもいろいろな要素が考えられるということです。
確かに、なにも勉強しないで(いわゆるノー勉)で受かるほど甘い資格ではありませんが、未経験者であったとしてもしっかり対策して臨めば誰であったとしても十分3級合格は狙うことができます!
試験の種類
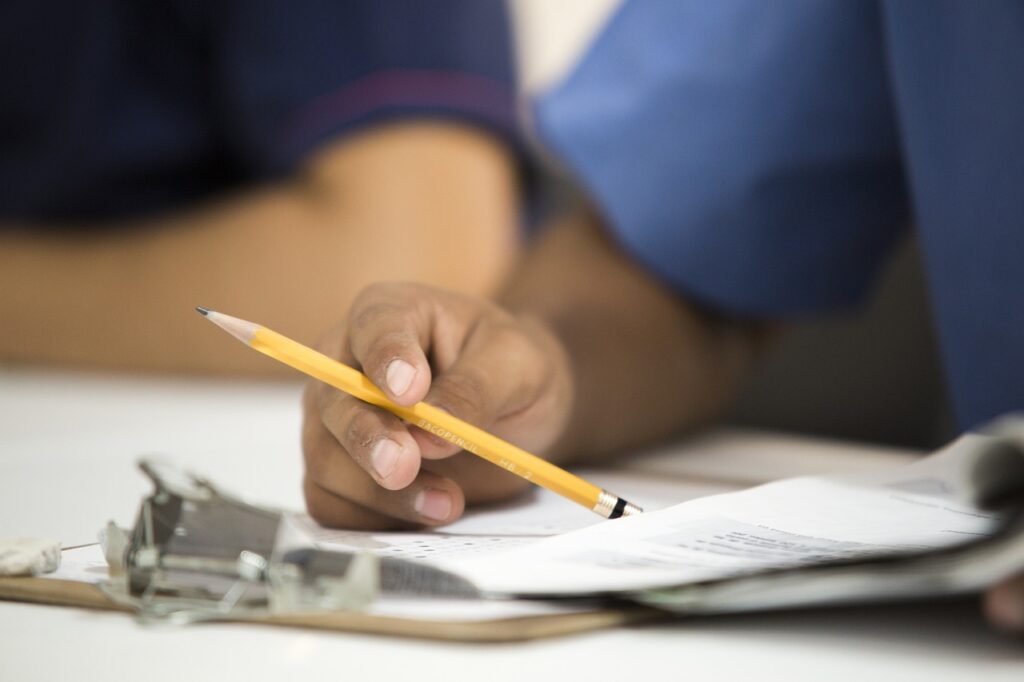
日商簿記の試験は、以下のように2つの形式で実施されています。
| 項目 | ネット試験(CBT方式) | 統一試験(ペーパー試験) |
|---|---|---|
| 試験日 | 随時(好きな日時を予約可能) | 年3回(2月、6月、11月) |
| 申込方法 | オンラインで試験会場を選び予約 | 所定の申込期間内に申し込み(団体・個人対応) |
| 試験会場 | 全国の指定会場(ネット試験対応のPC設置) | 試験会場(全国各地に指定のペーパー試験会場) |
| 試験時間 | 60〜90分(級により異なる) | 60〜90分(級により異なる) |
| 試験形式 | コンピュータで回答、即時採点 | 筆記試験(手書き) |
| 出題内容 | 公式テキスト準拠のランダム出題 | 試験委員会が作成した統一問題 |
| 合格基準 | 70点以上(100点満点) | 70点以上(100点満点) |
| 結果発表 | 試験終了後すぐに結果表示(合否が分かる) | 試験日から約2週間から1か月後に合否通知 |
| 受験料 | 2級:5,500円(税込) 3級:3,300円(税込) ※事務手数料550円 | 2級:5,500円(税込) 3級:3,300円(税込) |
| 試験の特徴 | 短期間で受験できる 予約が柔軟 一部変更後もすぐ反映 | 全国一斉試験 過去問が参考になる 会場受験 |
| 適した受験者 | 忙しい社会人やスケジュール調整が難しい人 試験日を柔軟に選びたい人 | 学生や一斉試験で集中して挑みたい人 過去問対策を重視したい人 |
ネット試験のメリット
ネット試験では統一試験と違い、随時好きなタイミングで受験ができるという大きなメリットがあります。
統一試験では決まった期間にしか受けられないので、受験するタイミングを調整する必要があったり、受からなかった時の再試験はしばらく後になってしまいます。
このことからネット試験は、精神的にも気軽に挑戦ができる受験方法であるといえます。
また、ネット試験だと合否が即日分かるのもメリットの1つです。この記事を書いている私のように「合否を早く知りたい!」という人にはネット試験がおすすめです。
注意が必要!
ネット試験は統一試験と違い、事務手数料が存在し各級の受験料に+550円がかかります。
また、受験する際のメモは会場側からもらった用紙に手書きで書くことになります。メモは手書きで解答はパソコンに入力という形になるため、やりづらさや違和感があるかもしれません。ある程度の対策は必要です。
まとめ
今回は簿記の種類と受験方法について解説しました。
簿記には初級から順に3級、2級、1級と進むにつれ取得難易度があがっていきます。
受験者数と合格率を見ると一般的には3級から受験する人が多いことが分かります。知識が全くない状態で一から勉強をして取得を目指す人も多いですが、しっかり対策することで十分合格を狙える難易度になっています。
また、試験にはペーパー式の統一試験とパソコンに入力するネット試験の2種類があります。両者の大きな違いは、受験の頻度と合否発表の早さが挙げられます。ネット試験には手軽に受験ができて合否がすぐに分かるメリットがありますが、パソコンに直接解答を入力する方法にやりづらさを感じる人は自分自身にあった受験方法を選定する必要があります。

